|
誠の昔調査最新報告 その2
再び、県立図書館にて『段別畝順帳』調査。
今回は『黒藤川村』を閲覧しました。
一応、『段別畝順帳』とは-
明治政府が租税改正を行った際、納税額を算出するために農地、山林を測量・記録した台帳です。
作成されたのは明治9年。
前回は川根村を閲覧し、虫食いだらけの和綴じ本の中から三浦藤吉の名を見つけました。
今回は、サカエ系の故里、黒藤川を調査です。
黒藤川の集落は、現在、久万高原町に属していますが、平成の合併前は柳谷村でした。
それ以前は久主(くす)村に属し、畝順帳が作成された明治9年頃は黒藤川村として独立していました。
現在、黒藤川は“くろふじがわ”と文字通りに呼ばれていますが、昔は“つづらがわ”と呼ばれていました。
図書館には“つづらがわ”で畝順帳を請求します。
図書館で畝順帳を請求してまず驚きました。
厚さ5センチの和綴じ本が4冊も出てきたのです。
川根村の8倍はあるでしょうか。
黒藤川は高知との県境近く、面河川沿いの山村です。
山の暮らしは貧しいものと勝手に想像していましたが、あっさりと覆されました。
分厚い本から“中岡”の名をすべて拾い出すのは一苦労でしたが、その際、気がついたことがあります。
思った以上に地名の数がものすごく多いことです。
人の家の数だけ地名があるんじゃないか、というくらい、沢山出てくるのです。
(おかげで、現在の住宅地図から拾った地名を元に中岡や西岡の名前を見つけられるんじゃないか、という甘い目論見は見事に打ち砕かれ、全てに目を通さざるを得なくなってしまいました。)
地名というのは、一種の文化です。
その由来は、土地土地に伝わる昔話であったり、風習、景色、暮らしなど、様々です。
地図から消えてしまった多数の地名に、黒藤川の暮らしが更に豊かだったことが感じられました。
現代の何丁目何番地なんてものはただただ分かりやすいだけで、ホント、味気なく感じてしまいました。
さて。
更に、更に、驚いたことがあります。
位牌の繰り出しから出てきた「中岡勘蔵」の名を拾い出してみたら、これまた次から次と出てくる出てくる。
三浦藤吉は、墓地と山林の2件のみでしたが、「中岡勘蔵」名義の物件は合計40件もあったのです!
(“中岡”姓の人物は、勘蔵のほかに「源蔵」のみ。
もしかすると源蔵は勘蔵と親戚関係なのかもしれません。)
| 整理番号 |
住所 |
種別 |
面積 |
㎡ |
坪 |
|
| 反 |
畝 |
歩 |
| 60 |
西之岡 |
畑 |
|
3 |
25 |
380.17 |
115 |
| 61 |
西之岡 |
墓地 |
|
|
10 |
33.06 |
10 |
| 67 |
下タ西ノ岡 |
伐替畑 |
|
1 |
10 |
132.23 |
40 |
| 91 |
西ノ岡 |
畑 |
|
3 |
25 |
380.17 |
115 |
| 97 |
西ノ岡 |
畑 |
|
|
15 |
49.59 |
15 |
| 118 |
上岡 |
畑 |
|
|
20 |
66.12 |
20 |
| 119 |
中岡 |
宅地 |
|
3 |
7 |
320.66 |
97 |
| 122 |
中岡 |
畑 |
|
8 |
26 |
879.34 |
266 |
| 135 |
ホド千 |
畑 |
|
1 |
15 |
148.76 |
45 |
| 149 |
ホド千 |
伐替畑 |
|
|
21 |
69.42 |
21 |
| 209 |
土井肥 |
畑 |
|
|
23 |
76.03 |
23 |
| 218 |
土井肥 |
伐替畑 |
|
|
12 |
39.67 |
12 |
| 288 |
谷肥 |
田 |
|
|
29 |
95.87 |
29 |
| 315 |
天神 |
田 |
|
1 |
3 |
109.09 |
33 |
| 323 |
シヨジ岩 |
田 |
|
1 |
2 |
105.79 |
32 |
| 813 |
一分片之下 |
畑 |
|
1 |
9 |
128.93 |
39 |
| 938 |
客之下タ |
畑 |
|
1 |
24 |
178.51 |
54 |
| 1015 |
太郎石 |
伐替畑 |
1 |
4 |
|
1388.43 |
420 |
| 1102 |
ゴンザ |
雑木山 |
|
|
15 |
49.59 |
15 |
| 1114 |
ナベラガモト |
伐替畑 |
|
1 |
|
99.17 |
30 |
| 1121 |
ゴンザ |
雑木山 |
|
|
12 |
39.67 |
12 |
| 1129 |
ナベラガモト |
雑木山 |
|
5 |
|
495.87 |
150 |
| 1202 |
ミヨトイワ |
雑木山 |
|
1 |
|
99.17 |
30 |
| 1274 |
亀ガ瀧 |
伐替畑 |
|
2 |
15 |
247.93 |
75 |
| 1294 |
ヨコ瀧 |
草山 |
|
2 |
|
198.35 |
60 |
| 1393 |
サカヲキ |
伐替畑 |
5 |
7 |
|
5652.89 |
1710 |
| 1425 |
イカダハ |
田 |
|
1 |
8 |
125.62 |
38 |
| 1426 |
イカダハ |
伐替畑 |
5 |
3 |
10 |
5289.26 |
1600 |
| 1426 |
イカダハ |
田 |
|
|
18 |
59.50 |
18 |
| 1445 |
サカイガ谷 |
伐替畑 |
|
2 |
|
198.35 |
60 |
| 1447 |
サカイガ谷 |
伐替畑 |
|
4 |
|
396.69 |
120 |
| 1513 |
山田 |
伐替畑 |
|
2 |
|
198.35 |
60 |
| 1741 |
水ガ谷 |
草山 |
5 |
5 |
|
5454.55 |
1650 |
| 1817 |
大畝 |
伐替畑 |
|
8 |
25 |
876.03 |
265 |
| 5003 |
オトコゼ |
草山 |
1 |
|
|
991.74 |
300 |
| 5053 |
宮ノシモ |
伐替畑 |
|
3 |
|
297.52 |
90 |
| 5065 |
シヨジヤク |
雑木山 |
|
2 |
|
198.35 |
60 |
※ |
| 5182 |
湯形 |
草山 |
|
7 |
|
694.22 |
210 |
|
| 5201 |
黒木 |
草山 |
|
7 |
|
694.22 |
210 |
| 5245 |
川崎 |
伐替畑 |
|
1 |
15 |
148.76 |
45 |
|
|
27087.61 |
8194 |
|
※併記=堀江新太郎
上記の表から、中岡って所に家があったこと(中岡に住んでるから中岡さんに?)、中岡家の墓地が西之岡という所にあることがわかります。
住所表記が現在とは異なるので、正確な場所は特定できません。
それぞれの物件は数十坪単位。
畑としてはさほど広いわけではありません(山間の段々畑として広いけど)。
けれど、合計40件、総面積はなんと、8194坪!!!
中岡家は結構な土地持ちだったことが判明いたしました。
驚きました!
照もミツもびっくりなその8200坪とは、どんな大きさかというと、よく聞く「東京ドーム何個分?」で表現すると、東京ドームの5分の3。
グラウンド部分だけで例えると、2つ分の広さに相当します。
さて。
40カ所も田畑があれば、一家ですべてを耕作・管理するのは容易ではありません。
察するに、沢山の小作人に土地を貸し出し、成果物である米や麦などの農作物の一部を小作料=地代として徴収していたと思われます。
つまり、「寄生地主」ってやつです。
明治9年頃の中岡家はとても裕福だったと思われます。
それがなぜ、貧乏になったのでしょう?
サカエからミツが聞いた話によると、それはサカエの祖父・栄吉の代に起きました。
栄吉がある日から仕事もせず、酒と賭け事にうつつを抜かすようになってしまったんだそうです。
原因は妻(ハルヨ)の死去。
よっぽど妻を愛していてめっちゃショックだったのか、それとも妻の死に何か負い目でもあったのか、詳しいことはまるっきりわからないのだけれど、ハルヨが亡くなったことを発端に、中岡家はどんどん落ちぶれていったいったそうです。
江戸時代、田畑永代売買禁止令によって土地の売買は(表向きには)御法度でした。
けれど、明治以降、個人に対し地券が発行され、土地を担保とした貸借も合法化され、自由に売買できるようになりました。
それが悪い方向に作用したのか、8200坪といっても40カ所に渡って細かく分散していたので、売買も容易、金銭にも換えやすかったものと思われます。
現在、三宅/三浦家に残っている(伝わっている)ものは中岡家のお位牌だけです。
|
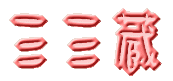 三宅と三浦で三三
三宅と三浦で三三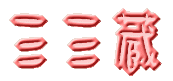 三宅と三浦で三三
三宅と三浦で三三